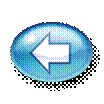|
その1「坂の上の雲」から収録した指揮・運用の考察 (要約) (航空自衛隊幹部学校記事1973年「昭和48年」1月号、3月号、 5月号、7月号、9月号、以上5回連続投稿) 力武 保光 (当時、航空自衛隊 幹部学校教育部教官) |
|
まえがき (まえがきの要約) 司馬遼太郎著「坂の上の雲」は、日露戦争のカゲの演出者である秋山好古陸軍少将(のち陸軍大将)と弟真之海軍中佐(のち海軍中将)を通じて、近代日本の勃興期―明治―という時代と、人間性を追及した物語である。私自身この著書に目を通したとき、読み進んでいくに従って、そのストーリーよりも随所に出て来る指揮・運用についての戦訓、あるいは指揮官の資質についての著者の考え方に、興味と関心を覚え、とくに諸作戦における指揮官及び幕僚の人間性を背景とした考え方には、他に類を見ない戦史書であるとすら感じ、この大作に敬服した次第です。 ――(中略)―― 本稿を書くにあたっては、当初このような私自身の考え方にもとづいて「坂の上の雲」の中で、指揮・運用、あるいは指揮官の資質など参考となる記事について朱線を書き入れて、その部分について繰り返して読んだ結果、これを何らかのカテゴリーに整理してみようと考えて、航空自衛隊教範「指揮運用綱要」と対比させて考察する試みに至った次第です。 従って本考察は、まず教範の見出しに応じて教範記載の要点を記載し、ついで「坂の上の雲」から、これら見出しに適応した記事を収録し、つづいて「教範と記事との関連」あるいは「教範の解釈等について補足事項の考察」を試みたものです。 (中略) 最後に、この収録については、著者司馬遼太郎氏のご好意により、幹部学校記事への掲載についてご了解をいただいたことに謝意を表する次第です。 |
本稿の要約 (昭和48年1月号投稿 ― 第1回目)
|
「項目(教範の記述)」、「収録記事の要約」、「考察の内容の要約」 |
|
第1章 指揮 1、指揮官の権限・責任 (教範) 指揮官は、任務を遂行するため指揮官にあたえられた固有の権限である。指揮官は、厳正にこれを行使しその職務を完遂しなければならない。 ○
指揮権の尊重 (4巻120頁から144頁) 203高地の攻防をめぐり、乃木軍の第3軍司令部の第1線の戦況の掌握の拙劣の状況から、総司令官大山巌の命令書を懐に秘め、総軍参謀長児玉源太郎大将が乃木大将に「第3軍司令官たる指揮権を一時わしに借用させてくれぬか」と統帥権の問題を熟知して、親友としての立場でこれを承知させた。 (内容のある収録記事です。是非原文をお読み下さい。) ――(考察)
―― 本項において収録した記事は、指揮官の権限に関する基本的な事項を包括している。 児玉大将が友人である乃木大将の軍司令官としての指揮権を一時的ではあるが、停止して自らが乃木軍を指揮することは明治陸軍創設以来の「統帥権」(天皇が親授する職)について、この指揮権を剥奪することは出来ない。 この難局を児玉大将はいかにして乗り切ったかを「指揮権の尊厳性」の面から考察しました。(考察した内容については軍隊組織の細部になりますので、省略します) 結果として児玉大将は砲兵陣地を大転換して203高地を1時間20分で占領した。 さらに、児玉大将は占領した203高地に登ろうとせず、全ては乃木希典の功績としたことは、統帥権に関する悪例を後世に残す愚を避けた、こととして後世の教訓となった。 |
|
2、指揮官と幕僚 (教範) 指揮官は、幕僚を掌握し、自己の分身としてこれを活用し、指揮の万全を期さなければならない。このため指揮官は、幕僚に対して、自己の意図を明示し、任務を明確に付与して、幕僚の能力を最大限に発揮させるとともに、その活動を組織的に行わせなければならない。 ○
指揮官への信頼感 (2巻243頁) 秋山真之が東郷平八郎と初対面した時、東郷は「この度のことは、あなたの力にまつこと大である」といっただけで、だまってしまった。真之はこの人物を一目見て「これは徳のある人物」だと感じた。 ○
幕僚の活用 (3巻21~22頁) 連合艦隊参謀長は海軍大佐島村速雄であったが、秋山真之が参謀団に加わったことを大いによろこび、全て君に一任する(作戦は天才がやるべきである)としてその後の、日露戦争の艦隊作戦はことごとく秋山真之がやったもので「旅順港外の奇襲戦」「仁川海戦」「3次にわたる旅順閉塞」「第2軍の大輸送」につづいて「日本海海戦」に至るまで、全て秋山の筆によって立案され、殆んど常に即座に東郷大将に承認されたものであった。 ○
幕僚道 (5巻68頁) 兄としての好古は東郷平八郎の参謀である弟真之に「参謀の要務は円転滑脱として上下との油にならなければならない。功名を断じて煩わしてはいけない」(自分の功名にするなということ) 真之のその後の生涯を見ると、彼は忠実にこれを守った。 ○
幕僚の心得 (4巻113頁) これは203高地の攻撃における児玉源太郎と乃木軍の第3軍司令部伊地知参謀長とのやりとりである。伊地知は203高地の攻撃が成功しないのは「旅順の戦況をもって第3軍司令部のみの責任にしようとなさるのは児玉閣下の卑怯というものです」「閣下は私が上申した砲弾量を満足に呉れたことがありますか」とのみ。これに対して児玉は「砲弾不足は、日本軍全体の問題だ。内地での生産の外、外国へ発注しているが、すぐ間にあわなくなる。その乏しい砲弾を野外決戦用と、この旅順攻撃用に配分しているが、必要の半分もまかなえない。「伊地知、日本は旅順だけで戦っているのではない。そんなことが分からないのか」 伊地知は「閣下のご責任を問いているのです」との発言。 児玉は「お前は女か」と児玉は立ち上がった。 自己中心的な視野しか持っていないという意味で児玉は言ったのであろう。 「砲弾が欲しいのは、どの軍も同じだ。与えられた条件で最善をつくすのが参謀長たる者の仕事ではないか」児玉はこれ以上長居をムダだと思った。 ○
幕僚としての責務 (4巻134頁) 児玉は第7師団司令部で、できるだけ精緻に戦況を知っておこうとした。児玉は前夜随行の田中少佐に命じ7師団の参謀に、「攻撃正面の地図をかかせておけ」と指示をしていた。すでにその地図はできている。児玉は天眼鏡をだして地図を見入った。 同じ中隊が左翼にも右翼にもいることを発見した。やがて師団参謀の書き間違いであることがわかった。書き間違いというより、其の参謀が現地を知っていない証拠であった。 軍司令部にせよ、師団司令部にせよ、この戦いを連戦連敗させている原因はここにあった。児玉は7師団の参謀に「貴官の目はどこについているのか」とどなった。「見ろ」児玉は地図の1ヶ所をたたいた。少佐参謀はやがて理由がわかったらしく顔を上げたが「しかし報告はそうなっております」と言った。「自分で見なかったのか」と児玉は他の参謀たちにもきかせるかのように大声を上げた。「参謀が第一線の突撃部隊の線までゆく必要があるだろうか」児玉はこの無言の問いを、すばやく感じた。「参謀は、状況把握のために必要とあれば敵の堡塁まで乗り込んでいけ、机上の空案のために無益の死をとげる人間のことを考えてみろ」児玉は帽子をつかんで部屋を出た。前線へゆくつもりであった。 ――(考察)
―― ここで収録した記事は、いずれも指揮官と幕僚の関係に関するもので、本来、この両者の関係は指揮官が指揮の中枢であり主体であるのに対して、幕僚はその補佐者であるといわれる。「幕僚制度設置の目的は指揮官の能力の限界を補佐するためのものであって、軍組織の規模の拡大ならびに機能の分化と複雑化に伴って、いわゆる指揮官の分身としての働きを主眼とするものと定義されています。 従って、指揮の成否は、幕僚活用の成否にあると言っても過言でなく、古来「すぐれた指揮官は幕僚を最もよく活用した指揮官である」といわれている。 幕僚の活用として収録した連合艦隊参謀長島村大佐が「作戦は天才がやるべきである」との認識のうえ、司令長官東郷大将の了解のもとに、すべてを秋山真之に一任し幕僚としての活躍の場を与え、その能力を最大限に発揮させ得たということは、幕僚活用の核心をついたものといえる。 兄としての好古は東郷平八郎の参謀である弟真之に対して、参謀たる者の心得について「参謀の要務というのは、円転滑脱として上と下の油にならなければならない」と説いていることは、部隊が指揮官の命令を良く理解し、実行の熱意を湧き立たせるには、部隊の気分と頭脳を司令部と同一程度に準備することが必要で、これは幕僚の任務である。このため幕僚は、指揮官と部隊から信頼され両者の確実な連鎖になることに、努めることを説いたものといえる。 乃木司令部における児玉大将と第3軍司令部伊地知参謀長の問答については、幕僚は自己の部隊のおかれている条件内で、最善をつくすことがあくまでも前提であり、いわゆる状況判断の過程における状況の分析を誤り「砲弾の不足が作戦の失敗につながる」ものとして責任を転換させており、本来の幕僚のあり方に関する一つの教訓が存在すると考える。 最後に収録した「幕僚としての責務」としての記事は、「参謀は状況把握のため必要とあれば、敵の堡塁まで乗りこんでゆけ」ということに関しては、状況が不利である方面または苦戦している第一線の現況確認は特別の配慮が必要であるし、重要な命令を下す場合には、指揮官自ら現地に赴くか、少なくとも有力な幕僚を派遣して戦場の真相をあらかじめ現地において確認しなければ、じ後、部隊に対する命令の権威を保つことが困難になることを意味し、このことを第一線の部隊の立場で考えた時、上級司令部が戦場の実情に合わない命令ばかりを下していれば当然、下級部隊としては感情的になるであろう。この感情をしずめるためには、たとえ実益がなくても、上級司令部の首脳が第一線に姿を見せることが、何よりも役に立つものと考える。 |
|
3、指揮官と部隊 (教範) 指揮官は、部隊を運用するにあたり、常に指揮系統を明確にし、指揮権の所在を明らかにして指揮の中断を絶無にするとともに、必要に応じて統制系統を確立し、各部隊の協同を律し、もって指揮の徹底を期さなければならない。 ○
部下統御法 (3巻92頁) マカロフは着任早々、自分の方針を全艦隊に徹底させた。「なぜ旅順艦隊は外洋に出ないのか」ということについては、前任者のスタルクはそれを水兵まで教えなかった。しかしマカロフは水兵にまで教えた。要するにバルチック艦隊を待っているのである。それを待ち2セットの艦隊が力を合わせて1セットの東郷艦隊を討つ。それまで湾内で自重する。 そこまではスタルクの方針とおなじである。「しかし私は単なる自重をせぬ。できるだけ短距離出撃し、できるだけ多く東郷のもち船を沈めておいて、きたるべき大海戦を有利にはこぶのだ」水兵達はこの大戦略に興奮した。「それにはこうする」とスタルクはいう。(以下略) ○
指揮官としての信望 (4巻221頁) ステッセルが降伏し、旅順が開場してから、ステッセル及びその麾下ほぼ3万の軍人の始末について、日本軍は国際法およびその慣例どおり、模範的としか言いようがないあつかいを行った。将校に対しては、捕虜として日本に送られるというごく普通の処遇のほかに、ロシア国へ送還するという処遇を用意し、その2つのうちいずれを取るかは本人の自由意志に任せた。この場合、軍人としての名誉を重んずる者はためらいなく捕虜になる道をとった。 なぜならば本国送還というのは、交戦中にはいっさい敵対行為はしない。ということを日本帝国に宣誓しての上のことなのである。 およそ軍人たるものが、戦時においてその敵国に対し敵対行為はしないと宣誓するなど、不名誉きわまりない行為であることにまちがいがなかった。が、ステッセルはそのほうを自ら選んだ。彼はそう宣誓し155日間共に戦った部下をすてて故国に帰った。ステッセルがその籠城中、麾下の将兵の人心を得ていたという事実はどうにも見つけにくい。軍隊心理からいって、戦闘中の軍隊で部下の信望を得るという原理は、ごく単純であった。もっともよく戦う指揮官であればいいというだけである。よくとは、勇敢でしかも的確な判断力をもち、戦闘を遂行する以外に余分の感情を持たないという条件が不可欠であった。「兵士というものは、ただ命令されるだけの可憐な集団だが、受身の立場であるだけに自分達を死地に連れて行く指揮官がどの程度の質のものであるかを見抜く臭覚はほとんど動物本能のように持っている。しかもかれらがつねに望んでいるのは、よき戦闘者としての指揮官であった。その命令に従っていくだけでその前途に勝利があるという信仰をもちうる指揮官であり、そういう場合、戦闘がいかに惨烈の極所にたちいっても、兵士は十分に耐えてゆく」旅順の下級将校をふくめ兵士達の大半が、自分達の運命の握り手であるステッセルの能力について「あの将軍では、戦争はうまくゆかない」ということを感じていた。 ――(考察)
―― 教範に記述されている「指揮官と部隊」は、指揮官が指揮の徹底を期すため、指揮系統を尊重すべきことを強調しているものであるが、本項において収録した記事はいずれも指揮官と部下の関係、すなわち指揮官として部下の統率法、あるいは指揮官としての部下からの信望を得るために、日頃から、指揮官として心掛けなければならないことに関するものである。 旅順艦隊におけるマカロフ提督は艦隊運用についての方針や戦術戦略を一兵卒に至るまで知らしめ、これによって各人が何をなすべきかを自ら悟らせ、戦意を盛り上げている。 このことはいうなれば指揮官と部下との意思の疎通であり、指揮官と部下の相互の理解と信頼を深め、部隊としての目的を達成するための重要な要件をなすものと考える。 指揮官は部下に対して、安易に命令や指示のみを与える弊に陥り易いものであるが、つとめてその職務や行動上の直接間接に必要な事項、および部下が興味や関心を持つ事項について、あらかじめ知らせるべきであり、その結果、部下が自らの職務についてその価値を見出すことにつながると考える。 これと対照的なのがステッセルについての収録記事である。 「指揮官としての信望」という表題を付しているが、指揮官にたいする部下の信頼は、部隊としての指揮の高揚のため、きわめて重要な要素であり、部下がその全てを指揮官に託しうると感じる時、これは、部隊の戦力として最大のものとなるのである。 「兵士というものは、・・・」 この内容は確かに統御の核心をついているものであり、指揮官に対する部下の信頼は、指揮官としての統御の全分野を通じて生まれてくるものと考える。 どのような組織であっても、上に立つ者が部下を知る以上に、部下は上に立つ者の能力や人間性を素早く見抜くものである。(以下略) |
|
4、指揮の要訣 (教範) 指揮の要訣は部下を確実に掌握し、明確な企図のもとに適時適切な命令を与えてその行動を律することにある。 この際、部下指揮官に対し、その能力を十分に発揮できる余地を与えることが必要である。 ○
部下への信頼と権限の委任 (5巻153頁) 提督としてのロジェストウェンスキーについていう。かれにはひとつの信仰があり、かれの部下であるすべての艦長がすくいがたい愚鈍者であると信じていることだった。 かれは自分の参謀達の能力さえ信じなかった。自分以外はすべて阿呆であるというこのふしぎな信仰は、他人がかれの容貌を錯覚したように、かれ自身もそれを錯覚することから生まれたものであるとしか思えなかった。とはいっても、ロジェストウェンスキーにはわずかながら気に入りの艦長がいた。ある駆逐艦の艦長のやることはすべて是認し大っぴらにその艦長のやり方をほめあげるばかりか、「かれに見ならえ」と、各艦長にいった。そのおそるべきえこひいきについては水兵までが知っていた。 ところが実際この駆逐艦の仕官や兵員から見れば、その艦長はだれでも見抜ける程度のハッタリ屋であり、艦の運用もまずく、その上へ兵員を無意味に酷使したり、怒鳴り付けたり、つまらないことを見つけると、その場で相手が死ぬほどなぐりつけたりした。結局この艦長は、実際の戦でもきわめて要領がよく、できるだけ危険を避け、殆んどろくな戦闘もせずに捕虜になった。 それとはまったく対象的な艦長がおり、部下の評判もよく、この艦長の能力と人物なら安心して命を託すことができるとすべての者が思っている艦長にたいして、ロジェストウェンスキーは過酷であり、つねに馬鹿よばわりをし、艦隊運動の演習中でも、水雷訓練をやっているときでも、はげしい嘲罵のことばをつづった信号をかかげてその艦長をからかい、ののしった。 ――(考察)
―― 教範に述べられている「指揮の要訣」は、部下を確実に掌握し、適時適切に命令を与えることであり、この際つとめて部下指揮官をして十分にその能力が発揮できるようにしなければならない、というものであるが、ここに言われている「部下指揮官に対しその能力を十分に発揮できる余地を与えることが必要」との意味はあくまでも、その部下指揮官の地位、能力および状況に応じてと、いう前提があってはじめて、いえることである。 ここに収録した記事は提督としてのロジェストウェンスキーが将帥として自己の部下指揮官の能力を見誤り、一平卒ですら見抜けるハッタリ屋である一駆逐艦の艦長の能力を過信し、かつ、またこれとは対照的に「この人なら安心として命を託すことができる」と、部下である全乗組員から慕われている艦長に対して過酷であり嘲罵のことばを使ったという事例であるが、ここに「指揮の要訣」の本質が存在すると考える。 すなわち教範にある「部下を確実に掌握し」といわれるゆえんは、指揮官として部下指揮官の能力なり、人間性なりを適切に見抜くことが、指揮の前提でなければならないし、これによってはじめて命令を与えて、その行動を律することができるものと考える。 上級指揮官といえども万能ではなく、その指揮能力には自ずと限度があるであろうし、また一方、これによって指揮を受ける部下指揮官も、彼自身の部下に対して指揮官としての責任を感じ、信念を持っているはずである。 さらに現場の状況については上級指揮官より、よく知っているのは当然であって、とくに戦時においては、混乱と錯誤が百出し、戦勢がつねに変転、一瞬の間に戦機を逸する実情を考えたとき、部下指揮官に対してその能力を十分に発揮できる余地を与えておくということも、重要な意義をもつものであると考える。 |
(以上、1973年―昭和48年―
航空自衛隊幹部学校記事 1月号投稿 ―第1回目― の要約)