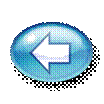その4 「坂の上の雲」から収録した指揮・運用の考察 (要約)
本稿の要約 (昭和48年7月号投稿 ― 第4回目 ― )
|
「項目(教範の記述)」、「収録記事の要約」、「考察の内容の要約」 |
|
第2章
運用 16、
作戦遂行の主眼 (教範) 防衛作戦一般の目的は、侵攻する敵を撃破してその企図を破砕するにあり、作戦の成否は航空優勢の帰すうに負うところがきわめて大である。 航空作戦は、わが国及びその周辺における航空優勢を獲得することを主眼として、もって防衛作戦全局における戦勢を制しなければならない。 ○ 戦略の主眼 (3巻7頁) 日露開戦にあたり、陸軍参謀本部の総長大山巌が作戦計画をたてている次長児玉源太郎に対し、「児玉さん、何度も申しますが、長くはいけませんぞ」ということを何度もいっていたが、 児玉はむろん百も承知でいた。戦いが長びけば日本の戦力は、からからに干しあがってしまい、日本は自壊するのである。要するに戦略の主眼は短期間にできるだけはなやかな成果をあげ、そのあと、外交でいう心理的契機をとらえて和平へもちこむというものであり、この主眼をはずれては、この戦争はまったく成りたたないことを、政府要人の全員が知っていた。 ○ 目的と目標 (3巻122頁) 乃木は、近代戦の作戦指導に暗い。しかしその性格は、いかにも野戦軍の統率にむいていた。 軍司令官はその麾下軍隊にとっての賛仰の対象であればよいということでは、乃木はそれにふさわしかった。 そのかわり、乃木には近代戦術の通暁者を配すればいいということで、薩摩出身の伊地知を参謀長にした。伊地知は多年ドイツの参謀本部に留学していた人物で、しかも砲兵科出身であった。砲兵科出身の幕僚長でなければ要塞攻撃に適任でないであろう。ところが、この伊地知が、結局は恐るべき無能と頑固の人物であったことが乃木を不幸にした。乃木を不幸にするよりも、この第3軍そのものに必要以上の大流血を強いることになり、旅順要塞そのものが、日本人の血を吸いあげる吸血ポンプのようなものになった。たとえば、海軍が献策していたのは、 「203高地を攻めてもらいたい」ということであった。この標高203mの禿山はロシアが旅順半島の山々を、ことごとくべトンでかためて砲塁化したあとも、ここだけは無防備でのこっていた。そのことは東郷艦隊が洋上で見ているとよくわかるのである。 「あれを攻めれば簡単ではないか」と、いうことよりも、この山が旅順港を見おろすのにちょうどいい位置をもっているということのほうが重大であった。203高地をとって、その上に大砲をひきあげて港内のロシア艦隊を射てば、2階から路上に石をおとすような容易さでそれを狙撃することができる。艦隊を追い出すために、陸から攻めるというのが陸軍作戦の目的である以上、203高地を狙うことが必要かつ十分な要件であった。 ところが乃木軍の伊地知幸介は一笑に付し、しかも「陸軍には陸軍の方針がある」として、この大要塞の玄関口から攻めこんでいくというような、真正直な戦法をとった。 ―― 考察 ―― クラウゼウィッツは、その著「戦争論」において、戦争の基本的要素とは闘争であるとし、さらに戦争とは、敵を屈服せしめて、自分の意思を実現するための行為であると、概念づけている。この戦争の概念は、現代においても何ら変わるものではなく、その本質は闘争にある。 「作戦」とは、このような闘争の場において、敵の暴力に対抗するための手段であって、戦いに負けては政略を成功させることはできない。このように先ず勝つことが先決問題であり、勝を前提として作戦を遂行することを、主眼とすべきである。 本項の「教範」の記述の内容は、あくまでも政略目的達成 (わが国の安全を全うすること)の手段として、作戦遂行の主眼 (努力目標) について述べているものであって、われわれは、この両者の本質的な関係を、十分に理解する必要がある。 この意味から、収録した記事のうち、「戦略の主眼」においては、日露戦争全局の作戦について、この戦争そのものを政略目的達成の手段であるとし、その戦略上の要求が達成できれば、直ちに和平にもち込むとした、当時の的確な戦争指導のあり方について一つの教訓があると考えると同時に、日露戦争そのものも、このように目的と目標の区分について、当時の政府要人が充分に理解していたからこそ、勝利をかち得たものであると考える。 「戦争の目的と目標」として収録した記事は、更にこの「目的と目標」について、作戦の一局面についての事例であるが、旅順攻撃の目的と、そのための作戦遂行の目標が一致せず、このため日露戦争そのものの政略目的である「早期和平」の達成目標に、少なからぬ影響を与えたことに関する記事である。 「目的はパリ、目標はフランス軍」というのは、前述のクラウゼウィッツが、目的と目標に関して力説した名言であるといわれている。これは、ややもすれば間違いやすい目的と、手段を明快に言ってのけたものであり、このような簡単なことがなかなか理解されず、数多くの拙劣な戦例を残しているのが戦史の実相である。 この収録記事において、クラウゼウィッツの名言を適用するならば、「目的は旅順、目標は旅順艦隊」とすべきであった。 旅順攻撃そのものが、「艦隊を追い出すために、陸から攻めるというのが、陸軍作戦の目的」であれば、終始一貫この線にそって目的を選定すべきであったと考える。ましてや「陸軍には陸軍の方針がある」として真正直な戦法に固執したことは、作戦遂行の主眼の設定と作戦指導についての拙劣な事例であるといえる。 |
|
17、部隊運用の要決 (教範) 部隊運用の要決は、戦機に投じて必勝の戦闘力を要点に集中指向し、その総合戦闘力を遺憾なく発揮させることにある。 部隊を運用するにあたっては、作戦の特性と航空防衛力の特質に応じ、戦いの原則を総合的に活用しなければならない。 ○ 部隊運用と合理的思考 (3巻11頁) すぐれた戦略戦術といえものは、いわば算術程度のもので、素人が十分に理解できるような簡明さをもっている。逆にいえば、玄人だけに理解できるような哲学じみた晦渋(かいじゅう)な戦略戦術は、まれにしか存在しないし、まれに存在しえてもそれは敗北側のそれしかない。 たとえていえば、太平洋戦争を指導した日本陸軍の首脳部の戦略戦術思想がそれであろう。 戦術の基本である算術性をうしない、世界史上まれにみる哲学性と神秘性を多分にもたせたもので、多分にというよりむしろ欠如している算術性の代用要素として哲学性を入れた。 戦略的基盤や経済的基盤のうらづけのない「必勝の信念」の鼓吹や、「神州不滅」思想の宣伝、それに自殺戦術の賛美と其の固定化という、信じがたいほどの神秘哲学が、軍服を着た 戦争指導者たちの基礎思想のようになってしまっていた。 日露戦争当時の政戦略の最高指導者群は、40歳以上の普遍的教養のあった朱子学が多少の役割をはたしているかもしれない。 朱子学は合理主義の者立場にたち、極度に神秘性を排する思考法をもち、それが江戸中期から明治中期の日本人の知識人の骨髄にまですみこんでいた。 しかし、日露戦争当時の政戦略の最高指導者群から30数年後の、太平洋戦争を指導した日本陸軍の首脳部は、その明治中期の群れとは、種族までちがうかと思われるほどに合理主義的計算思想から、かけ離れた指導者群となっていた。 ―― 考察 ―― 教範でのべられている部隊運用の要訣とはね「戦機に投じて必勝の戦闘力を要点に集中指向し,その総合戦闘力を遺憾なく発揮すること」であるとし、さらには、この部隊運用の要訣を前提として、諸種作戦の特性と航空防衛力の特質に応じ、戦いの原則を総合的に組み合わせ活用する柔軟な運用の必要性を強調したものである。 戦いの原則とは、古来幾多の戦史・先例から帰結された戦勝獲得のための基本的な原則であり、原因と結果との因果関係を追求した必然性と普遍性を持つ経験的な原理・原則である。 また、それは、数理学における公理公式的なものではなく、むしろ社会学的教訓の性格を持つものである。従って、これら諸原則は、現実の状況に即するように、健全な判断と戦術的識能とをもって適切に組み合わせて活用すべきものである。 航空自衛隊においては、この戦いの原則あるいは運用の基本原則として、とくに重要であると考えられるものは、教範の本項以降の項目でのべられているが、これらを列挙すれば「態勢の保持」「情報の優越」「主導と先制」「集中し機動」「統一と協同」「軽快と簡明」「通信連絡の確保」「航空防衛力の保全・充実」「天象・気象の克服・利用」「他自衛隊との協同」等とされている。 本項において収録した記事は、これら戦いの原則を適用し、活用する上において、あくまでも合理性、科学性に立脚したものでなければならないことを、示唆しているものであり、このような態度を堅持することによって、教範でのべられている部隊運用の要訣、すなわち「戦機に投じて必勝の戦闘力を要点に集中指向し、総合戦力を遺憾なく発揮する」というものが、戦いの原則と総合的に組み合わせ活用され、状況に即した戦術・戦略が生まれてくるものと考える。 |
|
18、
態勢の保持 (教範) 部隊は、常にその精強を維持して不敗の態勢を確立し、侵略を未然に抑止するとともに、情勢の緊迫に伴い、機を失せず作戦準備を整え、即応の態勢を堅持しなければならない。 緒戦の成否は、じ後の戦勢を左右する。このため作戦準備は、初動において戦闘力を最大に 発揮し、奇襲を防止することを主眼として促進するとともに作戦の終始を通じて絶えず先行的に補備増強し、応変の態勢を保持しなければならない。 ○ 戦術の大原則 (3巻67頁) 戦術の要諦は、手練手管ではない。日本人の古来の好みとして小部隊をもって奇策縦横大軍を翻弄、撃破するといったところに戦術があるとし、そのような奇功のぬしを名称としてきた。 源義経の鵯越の奇襲や、楠木正成の千早城の籠城戦などが日本人好みの典型であるだろう。 ところが織田信長やナポレオンがそうであるように、敵に倍する兵力と火力を予定戦場に集め、敵を圧倒するということが戦術の大原則であり、名将というのは、限られた兵力や火力を,そのような主決戦場にあつめるという困難な課題について、内や外に対しあらゆるかけひきをやり、いわば大奇術を演じて、それを実現しうる者をいうのである。あとは「大軍に兵法なし」といわれるように、戦いを運営してゆきさえすればいい。 日本の江戸時代の史学者や庶民が、楠正成や義経を好んだために、その伝統がずっとつづき、 昭和時代の軍事指導者までが専門家のくせに、この素人を好みに憑かれ、日本特有のふしぎな軍事思想をつくりあげ、当人たちもそれを信奉し、ついには対米戦をやってのけたが、日露戦争のころの軍事思想は、その後のそれとはまったくちがっている。 戦いの期間を通じて、つねに兵力不足と砲弾不足になやみ悪戦苦闘をかさねたが、それでも概念としては敵と同数もしくはそれ以上であろうとした。海軍の場合は、敵よりも数量と質において凌駕しょうとし、げんに凌駕したのであった。 ―― 考察 ―― 本項で「戦術の大原則」として収録した記事は、決戦場においては、彼我の戦力比較は、敵を圧倒することが戦術の要諦であるとするもので、いわば、敵にまさる優位な態勢の保持こそ、戦場において戦術を適用するうえで、重要な要件であることを示唆しているものである。 「大軍に兵法なし」といわれるのは、このような理想的なあり方をさすものであろう。 孫子の兵法にいわれ、誰もが一度は耳にしたであろう「彼を知り己を知れば、百戦あやうからず」とう「記述」の前文には「勝ちを知るに五つあり、以って与(とも)に戦う可(べ)きと、以って与(とも)に戦う可(べ)からざるとを知る者は勝つ。衆寡の用を知る者は勝つ――虞(ぐ)を以って不虞(ぐ)を待つものは勝つ。――と述べられているが、このことは、まさに態勢の優越こそ、戦勝の条件であるとする意味であり、彼我の戦力比較に応じて、戦うべきであるか、戦わざるべきかを誤りなく判断し、次に彼我の戦力の差の大小によって、その適用すべき戦術は、異なってくるもので、この点を十分に認識する必要があること。更には虞(ぐ)―われが充分な準備態勢の下に、綿密な計算の上で、敵の不虞―(敵の)不用意を静かに待ちうける、心がけがあることが、戦勝の要件であると述べているものである。 その上で孫子の兵法は「彼を知り己を知れば、百戦あやうからず―――」と述べているのであって、敵の備えている条件、その強弱をよく知り、われの実力を充分わきまえての戦いなら、いわゆる百戦百勝であると述べているものです。 (以下省略) |
|
19、
情報の優越 (教範) 情報の優越は、機を制して主動に立ち、戦勝を獲得するための不可欠の要件である。このため、平時から一貫した組織のもと、継続的に情報を収集し、敵の動きを未然に察知し、敵に先んじて準備し、初動において勝機を捕そくしなければならない。 ○ 情報の活用と固定概念 (4巻276~289頁) (これは、黒溝台会戦前、満州軍総司令部において取得した情報に関し、その価値判断を誤ったという拙劣な事例である) 戦線が、沙河の線で凍結している。「冬営」という軍事用語が、このときはじめてできたが、文字どおり、凍結であった。 日露両軍とも、長大な塹壕を掘り、柱をたて、その上に屋根をかぶせて掩体にし、風雪と砲弾に堪えるようにしていた。いわばこの両国家の大軍が、ことごとく地下陣地にもぐりこんでしまったようなかっこうであった。 ――(中略)―― このころ、日本の欧州における情報収集所はロンドンの日本行使館におかれ、この当時諜報のために欧州の各地をとびまわっている明石元二郎大佐なども情報はすべてロンドン送っており、それらの整理と日本への報告は宇都宮太郎から、再三にわたって、「ロシア軍は満州においてあらたな攻勢を準備しつつある」と東京の大本営に報告してきていた。大本営はそれを現地の大山・児玉に報らせた。 これらヨーロッパ経由の諜報に対する日本の満州軍総司令部の鈍感さは、おどろくべきものがあった。「ロシア軍が攻勢に出るなど、そんな馬鹿なことがあるか」という態度で終始した。 「この厳寒期に、大兵力の運動はとてもおこなえるものではない」というのが、その唯一の理由であった。この態度は参謀松川敏胤大佐が、最初からとりつづけていたるので、児玉源太郎は、この松川の能力を信頼するところが深く、「そのとおのだろう」と、彼もまたそう信じた。 戦術家が、自由であるべき想像力を一個の固定概念でみずからしばりつけるということは、 もっとも警戒すべきことであったが、長期にわたった作戦指導の疲労からか、それとも情報軽視という日本陸軍のその後の遺伝子的欠陥がこのころすでに芽生えはじめていたのか、あとから考えても彼等一団が共有したこの固定概念の存在は不思議なほどである。――(中略)―― 「第一、ロシア軍の習性は、日本軍のように大地を走りっぱなしに走って猛攻に猛攻をかさねるということはしない。かれらは大軍団が前へ進むと、そこで壕を堀り、杭を打ち、鉄条網をめぐらすといった陣地前進主義をとる。ロシア兵が、いかに腕力が強くとも、この凍った地面を相手に壕を掘るというような作業はできるはずがない。従ってかれらは春まで攻勢にでない」と松川敏胤は考えていた。児玉も同意している。 同意しただけでなく、いったんこの概念を作り上げると、頑固としてそれを動かさず、その概念を通してしか物事をみないために、それに反するという情報が入ってきても、「馬鹿をいうな」と拒絶反応のみを示した。 この概念は、たった一つの有力な証拠によって、充分粉砕できるものであった。 ロシア人が、ナポレオンの常勝軍をロシア本国にひき入れて撃破したのは、この冬季を利用したからであった。かれらの運動はむしろ冬季において得意であり、更にはその自軍の特性をロシア軍自身が伝統的に知っており、敵が冬将軍に悩まされているとき、かれらは一大反攻に出てくるのが戦史上の習性であった。 ――(中略)―― 日本軍の最左翼をうけもつ秋山好古は、騎兵の本務のひとつである敵情捜索を盛んにやっていて、ついには好古は永沼挺身隊という大規模な長距離挺身隊を派遣し、遠く蒙古地帯まで入り、敵の後方をまわって鉄道破壊や後方撹乱をやりつつ、情報をとるという冒険作戦まで実施した。このため好古のもとにはふんだんに敵のうごきについての情報が入り、そのつど司令部に報告した。とくにこのたびのロシア軍の攻勢についてはそれを推察しうる情報がふんだんにあり、そのつど報告したが、そのつど松川敏胤「また騎兵の報告か」と、ほとんど一笑に付し、一度といえども顧慮をはらわなかった。 「ロシア軍が、冬季攻撃をするはずがない」という、もはや信仰化したとさえいえる松川の固定概念であった。その理由のひとつは松川たちの疲労にもよるであろうが、ひとつには常勝軍のおごりが生じはじめたためであろう。 かつて、かれらは、強大なロシア軍に対し勝利を得ないまでも大敗だけはすまいと、小心に緊張しつづけたころは、針の落ちる音でも耳を澄ますところがあったが、連戦連勝をかさねていたために傲(おごり)が生じ、心が粗大になり、自然、自分が作りあげた「敵」についての概念に適さない情報には耳を傾けなくなっていたのである。 日本軍の最大の危機はむしろこのときにあったであろう。 ―― 考察 ―― 本項においてとして収録した記事は、黒溝台会戦前「ロシア軍が満州において、あらたな攻勢を準備している」という情報が、逐一満州軍総司令部にとどきながらも、司令部において固執したロシア軍の動きに関する固定概念から、その取得した情報を有効に活用する着意に欠けたという記事である。すなわち、情報はその性格として客観的事実に基づいたものでなければからないが、同時にこれら情報を取得し利用する側についても、あくまでも情報源とその内容を尊重し、みずからの固定概念に陥ることなく、これを積極的に利用すべきであるという、情報活動のあるべき姿を示唆しているものといえる。 教範で述べられている内容は、これらの基本姿勢をふまえたものであって、作戦指導の立場から情報及び対情報(わが情報の漏洩防止)の主眼とすべき事項を述べているものである。 すなわち「情報の優越は、機を制して主動に立ち、戦勝を獲得するための不可欠の要件である」と述べられているが、このことは戦勝獲得のためには、まず情報の分野において敵に勝つことが必要であるということを意味するものである。しかしながら、わが自衛隊に課せられている防衛作戦においては、作戦そのものが、受け身の立場を余儀なくされると同時に情報活動についても受動に陥る可能性がある。従って、「機を制して主導に立つ」ということが必要となり、なかんずく敵の初動を未然に察知することが、情報活動において最も重要なことと思われる。 孫子の兵法にも「明君賢将の動いて人にすぐれ、功をなすこと衆に出ずる所以の者は、先ず知ればなり」といわれ、かつ過去の幾多の戦例をみても、すべて先ず敵の実情を充分に予知したのちの戦いにおいては、じ後の作戦をきわめて有利に導いていることをみるとき、この情報の優越こそ、戦勝獲得のための不可欠の要件であるといえる。 このためにも、更に教範で述べられている「平時から一貫した組織のもと、継続的に情報を収集する」ことが重要であって、旧陸軍の戦闘綱要にも「情報活動を周到かつ有効ならしめるには、其の部署を組織的ならしめ、かつ其の実施を統一することを緊要とする」と述べられているゆえんがあると考える。 |
|
20、
主動と先制 (教範) 機を制し主動の地位に立つことは、戦勝獲得のための要道である。 このため、周密にして柔軟性のある計画のもと、機に先んじて準備し、積極的に敵に対するとともに、正奇の策をつくして敵の意表を突き、もって主動の地位を確保しなければならない。 ○ 機先を制する (1巻142頁) (これは明治陸軍の創設期、陸軍大学校に戦術教官として招へいされていたドイツ陸軍のメッケル少佐が、主導・先制について講義したという内容である) メッケルはいう。「戦いは出鼻で勝たねばならぬ」敵の意表に出て、その機先を制さねばならない。これについて更に「宣戦布告のあとで軍隊を動員するような愚はするな」ということを強調したが、となれば、軍隊を動員し、準備をととのえきったところで宣戦し、同時攻撃をし、敵が眠っている間に叩き、あとは先手、先手をとっていかなければならない。 ―― 考察 ―― 本項において収録した記事は「戦いは出鼻で勝ち、あとは先手、先手をとっていかなければならない」というものであるが、このことは教範で「機を制し主動の地位に立つことが、戦勝獲得の要道である」と、述べられていることに他ならないものである。 教範の内容を更に補足すれば、主動とは、おう盛な企図心をもつて自主積極的に行動し、敵を受動の立場に導き、戦勢を支配する地位を獲得することであり、また、先制とは、敵に先んじてわが方策を遂行することである。 そしてこの両者は、密接不離の関係にあり、相互に関連して、その成果をますます大きくし得るものである。 この主動・先制については、古来の優れた指揮官をみても、また、近く、第2次世界大戦初頭のドイツ軍の電撃作戦、あるいは大東亜戦争初期の日本陸海軍にみるごとく、いかに戦勝獲得のための重要な要件であるかが明らかである。 航空自衛隊においては、予測される作戦形態として、防勢作戦を旨とするものであるが、こと主動・先制の重要性に関しては、攻勢であれ防勢であれ、何ら変わるものではないと考える。 ただ一般的に防勢においては主動・先制の獲得が困難であって、ややもすれば消極受動に陥る可能性は存在するといえるが、個々の戦いの場における主動の立場を堅持し、先制を心掛けることは、戦勝獲得のための要道であることには変わりはない。 このため、作戦指導にあたっては、旺盛なる企図心と、敵の追随を許さない創意を心掛けるとともに、的確な判断によって戦機を明察することが重要であり、このことによってこそ、敵の意表をつき、その弱点に乗ずることが可能になると考える。 |
|
21、
集中と機動 (教範) 戦闘力を適時要点に集中発揮することは、戦勝獲得のためきわめて重要である。 このため、航空防衛力の特質を発揮して、集散離合を短切軽快に行い、すみやかに目的を達成しなければならない。機敏な指揮、迅速な機動、天象・気象の克服及び機宣に適する後方支援は戦闘力の集中を的確にするための要件である。 部隊を運用するに際し、所要に満たない戦闘力を逐次に使用することは、厳にこれを戒めなければならない。 ○ 主力殲滅主義 (1巻138頁) モルトケ戦術のあたらしさは、主力せん滅主義にあるであろう。戦場における枝葉の現象に目もくれず、敵の主力がどこであるかをすばやく知り、味方の最大の力をそこに集結させて一挙に攻撃しせん滅するというものであった。日露戦争における奉天会戦で日本陸軍がとった方法は、このモルトケの思想であるといってよい。 (注) モルトケ : プロイセン・ドイツ帝国の元帥、参謀総長 ○ 戦闘力の集中 (4巻83頁) 戦術にとってもっとも禁物なことの一つは、兵力を小出しに使用することであるが乃木軍司令部はつねにこの戦術上の初歩的な常識について無関心であることだった。 とくに第1師団が担当していた203高地攻撃については、それが唯一の失敗理由であった。第1師団としてその全力をあげて攻撃をさせることをせず、小部隊を逐次出させては,そのつどロシア軍の砲火に潰され、潰されるとまた小出しにだすといったあんばいであった。 ―― 考察 ―― 本項において収録した2つの記事については、前者は戦場においては敵が主兵力を配置しているところに味方も最大の戦闘力を結集させ、一挙にせん滅すべきであるというモルトケの主力せん滅主義と後者はこのモルトケ戦術に反して、乃木軍が兵力を小出しにしたという事例についてのものである。 この両者とも、いわば決戦場においては、敵に勝る戦闘力を発揮させることが戦勝獲得のための要件であることを示唆するものと考える。 この点については、すでに「態勢の保持」の項において考察した「大軍に兵法なし」ということにほかならないと考えるが、優勝劣敗は古今東西を通じての戦理である。 過去幾多の戦例をみても、一見小部隊をもって大部隊を破ったと思われるものでも、勝敗の岐路となった緊要の時期と場所においては、その戦闘力が優越していた事実を見逃すことはできないものである。 (以下省略) |
|
22、
統一と協同 (教範) 部隊の統一運用と相互の協同は、戦闘力を総合発揮するためきわめて重要である。 このため、目的を確立し、目標を確定し、一途の方針のもとに全機能を有機的に結合させ、 全部隊を緊密に協同させなければならかい。 指揮官は、一元的な指揮のもと、各部隊固有の能力を遺憾なく発揮させ、他部隊に対する理解と信頼を深めて、部隊相互の精神的結合を強め、もって統一と協同の実を挙げなければならない。 ○ 運用思想の一元性 (3巻11頁) (これは日露開戦のロシア側の戦術思想である) クロバトキンのことである。 このロシア側の出征司令官のたてた戦略戦術にも神秘性はない。日本軍に数倍する大兵力を満州に結集させるまでの間、ハルピンを最後の線として遼東以北、撤退につぐ撤退をかさねるという考え方は、おそろしいばかりに合理的である。 日本軍は無制限な北上をきらうことをクロバトキンは知っている。補給線が長くなり、弾薬食料の輸送もはかばかしくゆかなくなるうえに、会戦ごとに兵力消耗し、北上しきったあたりでは、よほど衰弱するであろう。それに日本は国力とぼしく長期戦にたえる戦力がないことを クロバトキンは知っている。 「最後にハルピンの線において衰弱しきった日本軍に対し、大兵力をもってせん滅的な打撃を与えて勝つ」というものであった。 もしロシア本国が強靭な意志をもって終始クロバトキンを支持し、その戦略を遂行しやすいように内政と外政の機能を充分に運転させたとすれば、おそらくは日露戦争の勝敗の位置は逆転していたにちがいない。 ただしロシア本国はそうではなかった。その上、日本側は彼我の問題点を充分に知りぬいており、短期決戦の主題をまもりぬく上で、内政と外政の機能が理想的に運転した。となれば日露戦争は一将軍の優劣問題など小さな課題であったといえるであろう。 ―― 考察 ―― ここに収録した記事は、日露戦争時における日露両国の統一運用思想の巧拙によって、その結果に影響をあたえたとする内容である。すなわち当時の日本において、国家目標を達成するための政策ひいては国家戦略が、当時の国力を前提として表裏一体にからみ合い、短期決戦という主題を守りぬくうえで、内政と外政の機能を理想的に運転されていたというものである。しかもこの短期決戦という目標に対して参謀本部と現地満州総軍の間には、何らの意見の相違もみられず一途の方針のもとに全機能を有機的に結合させえたものであるが、これと対象的なのが極東ロシア軍と本国との関係であり、これらの点に関しての日露両国の統一思想の有無が勝敗の原因につながったという内容の記事である。 この記事は、いわば指揮系統の上下にわたる一元的な指揮による「指揮の統一」、一途の方針による「行動の統一」の重要性を示唆しているといえる。 教範では、上記の内容に加えて、部隊間の統一・協同についても、その重要性を述べている。すなわち統一が上下・左右あらゆる面にわたって重要であるのに対し、協同は横の関係においても重要であるというものであり、この両者が相まって戦闘力の総合発揮を全うすることが可能となるものである。特に、航空自衛隊においては部隊組織が多元的であることにかんがみ、各級指揮官は統一と協同についての基本を理解するとともに、常にその実践を心掛けることが必要であると考える。 |
|
23、
軽快と簡明 (教範) 航空作戦は、その推移がきわめて迅速であり、作戦の成否は、戦機に投ずる軽快機敏な指揮と行動にまつところが大である。 ○
目的の単一性 (6巻130頁) A.T. マハンは、ロジェストウェンスキーの大航海については賞賛を惜しまなかったが、しかし戦闘指導者としてのこの提督についてはひややかな分析をおこない、とにかくかれが決戦前4日間においておかした誤りを執拗に指摘している。 「かれは目的の単一性を欠いていた」と、マハンはいう。敵に勝つという、この目的に対してあらゆる集中をおこなうべきこの知的作業において、ロジェストウェンスキーは二兎を追ったというのである。二兎とは「ウラジオストックへ遁走し、それによってたとえ残存兵力が20隻になったとしても極東の戦局に対して重大な影響をあたえうる」という目的が一兎である。 他の一兎は「東郷と対馬付近で遭遇するであろう。これと当然ながら戦闘を交える」という目的であった。 一行動が二目的をもっていた。一行動が一目的のみを持たねば戦いには勝てないというのが マハンの戦略理論であった。 マハンは東郷がこの「目的の単一性」という原則に忠実であったのに対し、ロジェストウェンスキーが二兎を追うためにその行動原理がきわめてあいまいになっていることを指摘しる。 「ロジェストウェンスキー提督がその目的の一つをウラジオストックへの遁走においたこはべつに悪くない。しかしその実現は確実に可能かといえば、当時の情況からみて蓋然性は存在しなかった。途中での戦闘は不可避であった。戦闘が不可避である以上、同提督としては途中の戦闘を想定しておくべきであった。しかし同提督は遁走と戦闘の二兎を追うがためにそれすらしなかった」 このことをやや解説風に述べると戦闘のためには艦の運動性をよくしておかねばならない。そのためには遁走用の満載石炭をへらし運動性の軽快さをとりもどさねばならなかったのに、同提督はそれをせず、このためどの艦も石炭をつみこみすぎ吃水が異常にさがっていた。 (注) A.T.
マハン:19世紀、米国の海軍軍人、著名な海軍軍事戦略家 ―― 考察 ―― 本項において収録した「目的の単一性」についての記事は、部隊を戦機に投じ軽快機敏に行動させるためには、まず目的が明確でかつ単一であることが望ましいというもので、古来「二兎追う者は一兎をも得ず」といわれる格言で代表される事例である。 このことはいわば教範でのべられている「軽快と簡明」のための前提というべきものとかんがえる。 作戦には、通常、混乱と錯誤をともなうものであり、このためにも目的が単一であれば部隊の行動は軽快機敏となり、指揮も容易となる。
(以下省略します) |
|
24、
通信連絡の確保 25、
航空防衛力の保全・充実 26、
天象・気象の克服・利用 (
以上3項目については、該当記事はなく省略
) |
|
27、
他自衛隊との協同 (教範) 他自衛隊等と協同して作戦を実施するにあたっては、達成すべき目標と協同の要領を明確にし、指揮統制組織を確立するとともに、部隊の行動について緊密な調整を行い、相互の信頼と理解のもとに協同の実を挙げなければならない。 ○ 陸海軍の強調 (3巻128頁) (これは第3軍が旅順攻撃の動きを活発にはじめて頃の、旅順におけるロシア陸海軍の状況である) ――艦隊、出てゆけ。と、旅順市街は酔っ払った陸軍の兵隊が、海軍の水兵をみると罵声をあびせたりする事件が頻発した。ときにはそれがもとで大げんかになり、法務官の世話になったりするが、陸軍の最高官であるステッセルは「陸軍の兵隊のいうことが当然だ」と、自分の幕僚に対していきまいたりした。 あるとき、艦隊が港外へ「出る出ぬ」ということで陸海軍の会議がひらかれたとき、ステッセルの感情がこうじてきて「私は軍を代表していう。東郷を撃滅するために、わが艦隊は出撃すべきだ。もし出撃せぬというなら、旅順艦隊は皇帝と祖国に対する反逆として罰せられるべきだ」とまで言った。 温和な艦隊司令長官ウィトゲフトはさすがに怒りのために感情の平衡をうしない、「申しておきますが、艦隊は陸軍中将である貴官の指揮下にはない。海軍の名にかけて暴言はゆるしません」 「海軍の名誉とは旅順の水溜りでアヒルのように昼寝をしていることですか」とステッセルは言い、ほとんどつかみあいの寸前の口喧嘩にまでなったことがある。 陸軍としては、艦隊にすわりこんでいられてはこまるのである。東郷はこの艦隊を目標に封鎖しているし、さらに乃木が背面からせめてきそうであった。艦隊さえいなければ日本軍はこうまでやっきになって旅順を攻めはしない。という気持ちが陸軍の兵士のはしばしにまであった。しかしながら、これはステッセルのおそるべき錯誤であった。なぜならば、ロシアは旅順港を海軍基地にした。軍港をまもるためには、まわりの陸地を陸軍が要塞化しなければならない。軍港にあっては陸軍は海軍あってのものでうり、ステッセルとしては海軍の作戦に対してもっと協調してやるべき立場にあった。しかしステッセルは海軍について、どういう同情ももたず、陸軍の利害のみを固執した。 ―― 考察 ―― 本項において収録した記事は、いわばロシア陸海軍間の相互信頼と理解の面での拙劣な事例である。航空自衛隊においても、主たる作戦は航空作戦であり、わが国及びその周辺における 航空優勢の獲得を主眼として遂行されるが、作戦の推移、状況の変化に応じ、他自衛隊との協同作戦を行う場合も考えられる。 この場合、教範で記述されている「達成する目標と協同の要領を明確にし、指揮統制組織を確立するとともに部隊の行動について緊密な調整をおこない協同の実をあげる」ことを充分に 着意することが必要である。 (以下省略します) |
(以上、1973年―昭和48年―
航空自衛隊幹部学校記事 7月号投稿 ―第4回目― の要約)